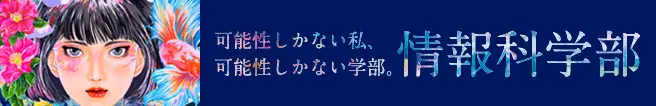マルトリートメントとは?子どもに与える影響や対策方法を詳しく



この記事について
マルトリートメントとは日本語で「不適切な養育」を意味する言葉で、子どもの健全な発育を妨げる行為のことです。
子どもの人権や健康を侵害する大きな概念で、児童虐待もマルトリートメントの一部に含まれます。
今回のコラムでは、マルトリートメントの定義やマルトリートメントにあたる行為の例、子どもへの影響などを解説します。
このコラムは、私が監修しました!

教授松原 三智子Matsubara Michiko医歯薬学 看護学
私は大学の中でも1年課程の「公衆衛生看護学専攻科」で「保健師」教育を主に行っています。
本学では4年生の大学卒業後、現場で中核的な役割を果たせる保健師の育成を目指して、「保健師」の資格を取得できるようにしています。その理由として、保健師は看護師の資格をベースに、個人や家族だけではなく、集団や地域そのものを看護するため、更なる学修が必要となります。保健師の仕事として感染症や難病などにも関わりますが、健康増進や予防など、何か問題や課題が起こる前に予防するという重要な役割があります。
私の研究は、保健師として乳幼児健康診査(以下、健診)に従事していた経験からスタートしています。健診は子どもの月齢に応じて行われますが、9割以上の親子が健診を利用しています。健診では、ほとんどの親が子どもの順調な発達を確認しつつ、不安なこと?気になること等を保健師に相談して笑顔で帰って行かれます。しかし、集団の健診であるからこそ、多くの親とは異なる対象と出会うことがあります。それは、笑顔を見せない親です。
このような親に継続して関わっていくと、ここで取りあげる「マルトリートメント」の状態になっていることも多く、マルトリートメントの果てとなる子どもの虐待死に至らないよう、健診などの場で気になる親子に丁寧に関わって支援することが重要です。
目次
 まず、児童虐待とは?
まず、児童虐待とは?
「児童虐待の防止等に関する法律」において4つの種類があります。
- 身体的虐待:子どもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
- 性的虐待:子どもにわいせつな行為をすること又は子どもにわいせつな行為をさせること
- ネグレクト:子どもの心身の正常な発達を妨げるような食事制限又は長時間の放置、欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心赌场-投注|平台以外の同居人による①②④の行為を知っていて放置すること、欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心赌场-投注|平台として監護を著しく怠ること
- 心理的虐待:子どもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力等、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
マルトリートメントとは?
「おとなの子どもへの不適切なかかわり」のことで、「身体的虐待と性的虐待を含む虐待(abuse)」「ネグレクト(neglect)」「心理的に不適切なかかわり(emotional maltreatment)」と分類して、上記の法律で定めた虐待の概念よりも広義な意味を示しています。
加えて、マルトリートメントの程度を、保護が必要な状態(A:レッドゾーン)、社会的支援が必要な状態(B:イエローゾーン)、「気になる子どもと親」として啓発?教育が必要な状態(C:グレーゾーン)に区分しています(高橋ら,1995)。
つまり、マルトリートメントはレッドゾーンにあたる虐待を含めて、もう少し軽度の不適切な関わりを含めたものであるということです。
そのため、マルトリートメントは、どこからレッドゾーンの虐待とするのか、またイエローゾーン、グレーゾーンも含めて境界を引くことは非常に難しいということがわかるでしょう。
虐待を含めてマルトリートメントは子どもの人権侵害です。
大人だけでなく、これから大人になり社会に出ていく中高生にも、ぜひ知っておいてほしい問題です。
 マルトリートメントは日常生活でも見かける行為
マルトリートメントは日常生活でも見かける行為
マルトリートメントとは、1980年代からアメリカなどで用いられるようになった言葉で、日本語では「不適切な養育」と訳され、子どもの健全な発育を妨げるような行為全般のことを指します。
子どもに暴力や暴言をふるう行為や、適切な環境を整えないネグレクトなどが虐待にあたることは皆さんよくご存じだと思います。
マルトリートメントはそういった明らかな虐待に加え、「虐待とは言い切れないけれど子どもの心や身体が傷つく行為、子どもをそのような危険にさらす行為」も含まれます。
具体的には以下のようなものもマルトリートメントに該当します。
- 子どもを怒鳴る、置いて帰ると怖がらせる
- しつけと称して子どもを叩く
- 大人の気分で子どもへの態度を変える
- 兄弟間で差別をする
- 子どもの話を聞かない、無視をする
- 子どもの前で夫婦げんかや、お互いの悪口をいう
- 子どもの意見を無視した教育方針や進路を押し付ける
- 入浴後に親が全裸で室内を歩く
(日本ではお父さんと女の子が小学校低学年くらいまで一緒にお風呂に入ることもありますが、諸外国だと4?5歳くらいまでが普通で、それ以降はNGとされることが多いです) - 子どもを放置してスマートフォンばかり見ている
- 幼児がいる家庭で高層マンションのベランダに踏み台となるようなものを放置する
- 親のたばこやライターを幼児の手が届くところに放置する
- 子ども乗せ自転車に子どもを乗せたまま自転車を離れる
「こんなこともマルトリートメントにあたるの!?」と驚かれるかもしれません。
マルトリートメントはごく一般的な日常生活の場面で起こり得るものです。
大人(親)の加害の意図の有無、子どものケガの有無にかかわらず、子どもの心と身体に危険や悪影響を及ぼす行為そのものが、マルトリートメントといえるのです。
過去の日本では「子どものためには多少厳しいしつけも必要だ」と、しつけのための体罰が容認されるような時代や考え方もありました。
しかし、エスカレートする体罰や虐待による悲しい事件を防ぐために、児童福祉法と児童虐待防止法の改正法が2020年4月に施行。
改正法には親権者からの体罰の禁止が盛り込まれ、「体罰等によらない子育てのために」というガイドラインが策定されました。
 マルトリートメントが子どもに与える影響
マルトリートメントが子どもに与える影響
マルトリートメントは、子どもの心と身体に悪影響を及ぼすことが明らかになっています。
幼少期に親からマルトリートメントを受け、心が傷つき親子の愛着がうまく形成されないと、愛着障害につながるといわれています。
つまり、親子の愛着形成がされていないために、他者との人間関係もうまく作れず、問題行動や対人関係?情緒面が安定しない状態を引き起こすこともあります。
また、過度のマルトリートメントは脳が傷ついたり、脳が萎縮したりと、脳に物理的な影響があることもわかっています。
また、虐待されている際には心を守ろうとして、自分がその場にいない状態(解離)になり記憶がないなども起こり得ます。
マルトリートメントがトラウマとなって大人になってから心のトラブルを発症したり、脳の傷、委縮により意欲低下や落ち着きがなくなったり、対人関係のトラブルを引き起こしたりすることがあるといわれています。
このように、マルトリートメントは子どもへの直接的な影響が見えにくいものもありますが、子どもの心と身体に影響を与えてしまいます。
 マルトリートメントにはどう対策する?
マルトリートメントにはどう対策する?

マルトリートメントは、軽微なものも含めてごく日常の場面で起こり得るものです。
親は虐待と思っていなくても、実は子どもを傷つけてしまう接し方をしている可能性があることを忘れず、子どもと接することが必要です。
大人が「もしかしてマルトリートメントをしているかも?」、そして子ども自身が「これってマルトリートメントかも?」と思った場合は、家族や友人と話してみたり、子育て支援センターや児童館、スクールカウンセラー、自治体にある保健センターや児童相談所などに相談してみたりするのも良いでしょう。
また、マルトリートメントは、子育ての不安や孤独などが引き金となっているケースもあります。
自治体や児童相談所などの関係機関による、欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心赌场-投注|平台に対しての啓発活動や相談といった支援も重要です。
 マルトリートメントとは子どもの健全発育に悪影響のある行為
マルトリートメントとは子どもの健全発育に悪影響のある行為
マルトリートメントとは、子どもに悪影響を与える不適切な行為全般を指します。
虐待やネグレクトはもちろんですが、子どもの前で夫婦げんかをする、しつけとして大声で怒鳴る、親の気分で態度を変える、親の考える進路を押し付けるなど、日常の中でよく見かける行為もマルトリートメントに含まれます。
マルとトリーメントは子どもの心を傷つけ、心や身体に悪影響を与えます。
幼少期に親と適切な関係を築けなかったために愛着障害を起こして人間関係をうまく作れなくなったり、脳に傷や萎縮が発生してトラウマや問題行動となって現れたりしてしまいます。
マルトリートメントは、まず、誰にでも起こり得るものです。
したがって、教員や欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心赌场-投注|平台、子ども自身がマルトリートメントを正しく理解することで、マルトリートメントの状態にある親子を早期に発見することにつながります。
そのためには、子ども自身が正しい知識を知って、自分がマルトリートメントの状態にあるのかどうかを判断し、マルトリートメントを受けている際には声を挙げて、保護が受けられるようにしていくことが重要です。
 マルトリートメントについて、わかりやすい出前授業があります
マルトリートメントについて、わかりやすい出前授業があります
北海道科学大学保健医療学部看護学科の松原 三智子教授が本記事と同じテーマの「マルトリートメント(子どもの虐待と気になる親子)とその支援について」講座を行なっています。
「子どもの虐待は急増しています。虐待の定義は境界が難しく、「マルトリートメント」という気になる親子の様子を含めて解説し、具体的に気になる親子に遭遇した際、どのように関わるとよいかについて解説します。」
高等学校をはじめ中学校?小学校の関係者の方でご興味のある方はぜひ下記からお問い合わせください。
北海道科学大学出前授業ページ
北海道科学大学保健医療学部看護学科では、幅広い対応力を持つ次世代の看護師を育成します。
北海道で看護師を目指す方は、ぜひ保健医療学部看護学科、公衆衛生看護学専攻科へお越しください!