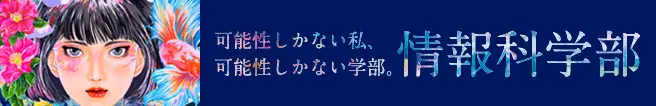薬が効く仕組みを解説!効き方の種類や用法用量を守る重要性も



この記事について
私たちが病気やケガの治療のために使う薬。
飲んだ薬がどのように体に作用して症状を改善してくれるのか、不思議に思ったことはありませんか?
薬には、体の中で効果を発揮するための精密な仕組みがあります。
今回のコラムでは、薬が効く仕組みを解説。
薬を飲んでから効果が出るまでの流れや効き方の種類、そして用法用量を守ることの重要性について、わかりやすくお伝えします。
薬についての理解を深め、より安全で効果的な服用につなげましょう。
このコラムは、私が監修しました!

准教授髙栗 郷Takaguri Akira薬理学
私は北海道薬科大学大学院を修了後、米国テンプル大学医学部心臓血管センターに博士研究員として留学しました。それ以来、動脈硬化をはじめとする心血管疾患の病態解明や、治療標的となる候補の同定に取り組んでいます。
心血管疾患による死亡率は、日本のみならず世界的に依然として高く、その克服は重要な課題です。特に私は、病態のさらなる解明が急務とされ、治療薬の選択肢が限られている腹部大動脈瘤や急性大動脈解離に注目し、細胞や遺伝子改変マウスを用いた研究を進めています。さらに、体内時計を司る時計遺伝子の発現の乱れが心?腎疾患の発症に与える影響の解明にも関心を持ち、研究を行っています。
目次
 薬が効く仕組みとは?飲んだ薬はどうなる?
薬が効く仕組みとは?飲んだ薬はどうなる?
薬は主に、口から飲む内服薬や、皮膚や粘膜に直接塗ったり貼ったりする外用薬、血管内に直接入れる注射薬の3種類に分けられます。
内服薬を例にとると、私たちが服用した薬は胃で溶けて主に小腸で吸収されます。
吸収された薬の成分は血液の流れに乗って全身を巡り、患部など目的の場所に到達して作用します。
薬が作用する際に重要となるのが、「伝達物質」と「受容体」の仕組みです。
体の細胞にはさまざまな「受容体」があり、伝達物質が受容体と結合することで細胞に必要な指令を伝えています。
患部に到達した薬は、この伝達物質の代わりに受容体と結合したり、逆に伝達物質と受容体の結合を阻害したりすることで効果を発揮するのです。
その後、薬の成分は再び血液とともに全身を巡り、徐々に肝臓で代謝(分解)されていき、最終的には、尿や便、汗などとともに体外に排出されます。
 薬の効き方にも種類がある
薬の効き方にも種類がある
薬は、伝達物質と受容体の結合で起きている反応を強めたり阻害したりすることで効果を発揮しています。
薬の効き方とその具体例について、主な2種類をご紹介します。
体の反応を促す:作動薬(アゴニスト)
薬の成分が伝達物質の働きを模倣して受容体と結合し、体の反応を促します。
例えば、ぜんそくの薬はその成分が交感神経の受容体と結合して神経細胞に働きかけ、気管支を広げて呼吸を楽にします。
体の反応を抑える:拮抗(きっこう)薬(アンタゴニスト)
薬の成分が伝達物質と受容体との結合を阻害し、体の反応を抑えます。
拮抗薬として代表的なものは抗アレルギー薬です。
アレルギー反応の原因となる伝達物質ヒスタミンが受容体と結合するのを阻害し、血管の拡張を抑えてアレルギー症状を抑えます。
副作用が起こる理由
薬の副作用が起こることも、薬が効く仕組みが関係しています。
副作用は、目的とする場所(患部)以外に、同じ種類の受容体が存在することで起こります。
例えば、ヒスタミンの受容体は脳にも存在しています。
ヒスタミンは、脳内では、覚醒や集中力アップに関わるもの。
そのため、抗アレルギー薬を服用すると、脳内のヒスタミン作用が阻害され、副作用として眠気が出てしまうのです。
 薬が目的の場所で効果的に作用する仕組み
薬が目的の場所で効果的に作用する仕組み

薬は血液に乗って全身を巡るため、前述したように目的の場所以外に作用してしまうことがあります。
また、薬の成分によっては途中で胃に影響を与えたり、逆に胃酸によって効果が弱まったりする可能性も。
そこで、現代医療では「必要な量を、必要な時間で、必要な部位に届ける」というドラッグ?デリバリー?システム(DDS)の考え方に基づき、薬をより効果的に患部へ届けるための工夫がなされています。
DDSでは、以下の3つの考え方から、さまざまな技術や工夫が開発されています。
放出制御
必要な量の薬を効率的に提供する技術です。
1日1回の服用で1日効果が持続する薬など、長時間にわたって有効性を維持する技術が開発されています。
単に用量を増やすのではなく、分解時間を長くするなどの工夫が施されています。
吸収改善
必要な場所へ効率的に届ける技術です。
具体的な例では、薬の形状や構造を工夫することで、必要な場所での吸収効率を高めています。
例えば、腸で溶ける腸溶錠やカプセル錠、口の中で溶ける口腔内崩壊錠、湿布薬や塗り薬、注射薬など、さまざまな形状が用いられています。
ターゲティング
薬の効果を目的の場所だけに作用させる技術です。
特定の抗原とだけ特異的に結合する抗体を薬の運び手として利用するといった技術が開発されています。
ほかの場所への作用が抑えられるので副作用のリスクが低く、より強い効果を期待できます。
 薬が効く仕組みを知れば用法用量を守る重要性がわかる
薬が効く仕組みを知れば用法用量を守る重要性がわかる
薬は、薬の成分の血中濃度が適切な範囲(有効濃度)にあるときに、最も効果的に作用します。
例えば、1日3回服用の薬は、およそ4?6時間効果が持続するよう設計されています。
また、薬の成分が代謝?排出されて血中濃度が下がるまでには、薬を飲んでから6~8時間ほど。
薬の用法?用量が決められているのは、有効時間?排出時間に合わせて血中濃度を維持し、安全に使うためです。
服用間隔や量を守らないと、血中濃度が保てずに効果が得られなかったり、逆に血中濃度が上がりすぎて副作用が出てしまったりするのです。
医師や薬剤師の指示通りに服用することが、安全で効果的な治療につながります。
 薬が効く仕組みを理解して安全で効果的な服用を
薬が効く仕組みを理解して安全で効果的な服用を
薬が効く仕組みは、体にさまざまな指令を出す伝達物質と受容体の仕組みに関係しています。
吸収されて血液に乗って全身を巡る薬の成分は、薬が伝達物質の代わりに受容体と結合して体の反応を促す指令を出したり、逆に伝達物質と受容体の結合を阻害して体の反応を抑えたりすることで、効果を発揮しているのです。
薬は「必要な量を、必要な時間で、必要な部位に届ける」のが理想とされ、必要な場所で効果的に作用するためにさまざまな技術が開発されています。
血中の有効濃度を維持して薬の効果を適切に得るためにも、用法用量を守って服用することが大切です。
 北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科の高栗 郷 准教授の講座「薬はどのように体に作用するのか?」では、私たちが薬を体内に取り入れると、薬は体内でどのような運命をたどり、最終的にどこに行き着き、病気を治す作用を発揮するのかを解説。
薬の作用を体系的に学べます。
北海道科学大学薬学部薬学科では、薬学教育モデルのコアカリキュラムのほか、独自のカリキュラムをご用意しています。
他学部生との協働学習や、臨床経験豊富な教員による実践的な教育を通じて、多角的な視点と専門性を養えるのが北海道科学大学の薬学部薬学科の特徴です。
超高齢化社会を迎え、薬剤師の存在感や必要性が高まっている中、地域医療を担う一員として、高い専門知識と使命感を持った医療人を育成します。