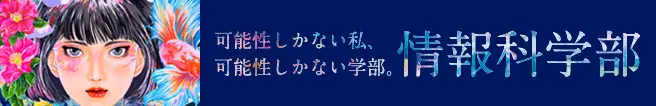花粉症の原因とは?メカニズムや治療法を解説



この記事について
春になると多くの人を悩ます花粉症。
くしゃみや鼻水、目のかゆみなどの症状に悩まされた経験がある人も多いのではないでしょうか。
花粉症のさまざまな症状は生活の質を大きく低下させますが、その原因やメカニズムを理解し、適切な対策を取ることで症状を和らげることもできます。
今回は、花粉症の原因やメカニズム、そして治療法について詳しく解説します。
最新の治療法もご紹介しますので、花粉症でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。
このコラムは、私が監修しました!

教授山下 美妃Yamashita Miki医療薬学
薬剤師は、病気を抱える患者さんの病気の治療や生活者(健康な人)の健康維持に、非常に重要な役割を果たしている職種にもかかわらず、国民にはそれが十分に知られていないのが現状です。
私は、国民に薬剤師の役割を十分に理解してもらい、その価値を高めるために、「薬剤師業務の質を上げること」、「薬剤師の役割を社会に対して“見える化”すること」の2つが重要だと考えています。
薬剤師業務の質を上げるためには、研究データ等のエビデンス(根拠)を活用して、薬剤師業務を行う必要がありますが、これらエビデンスは不足している場合が多いので、私は、このエビデンスの創出に取り組んでいます。
また、薬剤師業務を社会に対して“見える化”するために、薬剤師が患者の病気の治療や生活者(健康な人)の健康維持に関わることで、どのような効果があるのかを研究によりデータ化し、公表するという取り組みを行っています。
目次
 花粉症とは
花粉症とは
花粉症は、正式名称を「季節性アレルギー性鼻炎」といいます。
私たちの体が花粉を「危険な異物」と認識してしまい、体内で過剰な免疫反応が起こることで発症する病気です。
花粉に反応して起こる症状には、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみや充血などがあります。
季節性アレルギー性鼻炎と通年性アレルギー性鼻炎の違い
アレルギー性鼻炎は大きく分けて2種類あります。
花粉などが原因となって特定の季節に症状が出る「季節性アレルギー性鼻炎」と、1年を通じて症状が続く「通年性アレルギー性鼻炎」です。
通年性アレルギー性鼻炎の主な原因は、ハウスダストやダニなどです。
最近では、この2つのタイプをあわせ持つ人も増えており、年間を通じて症状に悩む方が増加しています。
 花粉症の原因?メカニズム
花粉症の原因?メカニズム
花粉症は、体内での免疫反応によって引き起こされる病気です。
花粉症の対策を講じるためにも、まずは症状が起こるメカニズムを理解しましょう。
鼻の症状が起こる仕組み
花粉が鼻に入ると、花粉に含まれる特定のタンパク質(アレルゲン)が鼻の粘膜から細胞内に入り込みます。
細胞内では、アレルゲンに対する「抗体」が産生され、「マスト細胞」と呼ばれる細胞に結合します。
その後、再びアレルゲンが体内に侵入すると、マスト細胞からヒスタミンやロイコトリエンといった化学物質が放出。
これらの物質が神経や血管に作用することで、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状が現れます。
目の症状が起こる仕組み
目の症状も、鼻と同様の仕組みで起こります。
特に、まぶたの内側にある結膜には、アレルギー反応を引き起こす免疫細胞が多く存在するだけでなく、目は常に涙で潤っているために、入ってきたアレルゲンが溶け込みやすいことなどから、アレルギー反応が起こりやすいといわれています。
鼻と同様に、花粉が目に入ると、アレルゲンが結膜に入り、マスト細胞から化学物質が遊離することで、かゆみや充血、涙目などの症状を引き起こします。
 花粉症を発症する人が増加している理由
花粉症を発症する人が増加している理由
日本では、花粉症の患者数が年々増加傾向にあります。
この背景には、複数の要因が関係しています。
環境の変化
2019年に行われた全国疫学調査では、花粉症の有病率は42.5%であり、38.8%の人がスギ花粉による花粉症と報告されています。
日本では、戦時中や戦後の過度な伐採により荒廃した山地の復旧や高度経済成長期における木材需要の増大から、成長の早いスギが多く植えられました。
日本の森林面積の約18%がスギであり、これは国土の約12%の面積といわれています(欧洲杯买球官网_澳门金沙城中心赌场-投注|平台4年3月31日現在)。
現在、これらのスギが成長し、木材としての使用に適した時期を迎えて大量の花粉を飛散させています。
また、近年の気候変動の影響で、花粉の飛散量も増加傾向にあります。
生活環境と習慣の影響
現代の食生活や生活リズムの乱れも、花粉症の増加に関係していると考えられています。
食事内容の欧米化や、睡眠不足?ストレスの増加による自律神経の乱れなどが、私たちの免疫機能に影響を与えています。
また、都市部では排気ガスの影響で、花粉症を発症しやすい環境になっているという指摘も。
排気ガスに含まれる微粒子と花粉を一緒に吸い込むことで、アレルギー反応が出やすくなるといわれています。
 花粉症の治療法
花粉症の治療法

花粉症の治療は、原因となる花粉の回避、症状を一時的または長期的に緩和する治療法に大きく分けられます。
医師と相談しながら、自分に合った治療法を選択することが大切です。
花粉の回避
花粉症の第一の対策は、まず花粉を避けること
以下のような方法で、可能な限り花粉の体内への侵入を防ぎましょう。
- 自分がどの花粉(アレルゲン)に対する花粉症なのかを知る(病院で検査が必要)
- 花粉情報を確認し、飛散量が多い時はできるだけ外出を避ける
- マスクの着用
※鼻の穴の中に入れて、花粉の侵入を減らすマスクも。 - メガネの使用
※レンズの周りにフードがついており、花粉が目に入りにくい構造のメガネも。 - 外出後は衣服を払い花粉を落とす、すぐに着替える
- 花粉が付着しにくいポリエステルなどの衣服で外出する
- 掃除による花粉の除去
規則正しい生活やバランスの取れた食事、適度な運動やストレス発散も有効です。
症状を緩和する治療
症状を緩和するためには、薬を使った治療を行いますが、これらはあくまで一時的に症状を抑えるだけで、根本的な治療ではありません。
症状や程度に応じて、以下のような治療薬があります。
- アレルギー症状を抑える飲み薬
- 鼻や眼に直接使用して、アレルギー症状を抑える点鼻薬、点眼薬
新しい薬!
【オマリズマブの皮下注射製剤】
アレルゲンに対する「抗体」がマスト細胞に結合するのをブロックすることで、アレルギー反応を抑える薬。
スギ花粉症で、飲み薬や点鼻薬で効果が認められない重症度の高い患者さんのみが使用できます。
?【エピナスチン眼瞼クリーム製剤】
上下のまぶたに塗ることで、アレルギー性結膜炎の症状(目の痒み、充血)を抑える塗り薬。
1日1回塗るだけなので、点眼薬が苦手な子どもや高齢者にも使いやすいです。
これらの薬には様々な種類があり、どの症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)に対する効果が高いか、効果の強さ、効果が現れる時間の速さなどが異なります。
また、花粉が飛び始める前から使用を開始することで、より効果的に症状を抑えることができる薬もあります。
一部の飲み薬では、眠気が強く出るため、自動車などの運転を避けた方が良いものもあります。
医師や薬剤師に確認、相談してから使用するようにしましょう。
症状が軽い場合や症状の出始めの時期にはドラッグストアなどで購入できる医薬品でも対応できますが、病院で適切な検査を受けたうえで、病状のタイプや重症度に合った治療を受けることが、重症化を防ぐために重要です。
上述の薬物療法とは異なり、長期的な症状緩和を期待できる治療法として、アレルゲン免疫療法があります。
アレルゲン免疫療法には、注射薬を使用する治療法と、舌の下に液体の薬や錠剤を入れる治療法の2種類があり、アレルゲンを少量から、徐々に量を増やし繰り返し投与することにより、体をアレルゲンに慣らし、症状を和らげる治療法です。
推奨される治療期間は 3?5 年と長くかかるものの、8割の患者さんに効果があると報告されている有効な治療法のひとつです。
ただし、舌下免疫療法はスギ花粉症とダニアレルギーの患者さんのみが受けられる治療法です。
特に、スギによる花粉症に悩んでいる方は、ひとつの選択肢として医師と相談してみてはいかがでしょうか。
 自身がどの花粉に対する花粉症なのかを知り、花粉の回避をベースにした適切な薬物治療を
自身がどの花粉に対する花粉症なのかを知り、花粉の回避をベースにした適切な薬物治療を
花粉症は、花粉に対する免疫システムの過剰な反応により起こります。
花粉が体内に取り込まれると、花粉に含まれるアレルゲンに細胞が反応してヒスタミンなどの物質を放出。
これらの物質が神経や血管に作用して、アレルギー症状が現れます。
環境や生活習慣の変化により花粉症の患者数は増加していますが、さまざまな治療法が確立されてきています。
医師の診察?検査を受け、花粉の回避とともに、症状や生活スタイルに合わせた適切な治療法により、花粉症の症状を効果的にコントロールすることが可能です。
 北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科では、花粉症を含むさまざまな疾患やその治療に必要な薬学の知識や技能を総合的に学ぶことが可能!
また、12名の専門薬剤師、認定薬剤師が教員として在籍しており、実務経験豊富な教員や現役で医療施設に派遣されている教員が、今まさに現場で行われている鮮度の高い学びを提供しています。
北海道科学大学薬学部薬学科は、薬剤師国家試験合格率は87.2%(過去5年実績平均)と、全国平均を上回る高い合格率を誇っており、地域住民の健康を支える薬剤師を育成しています!